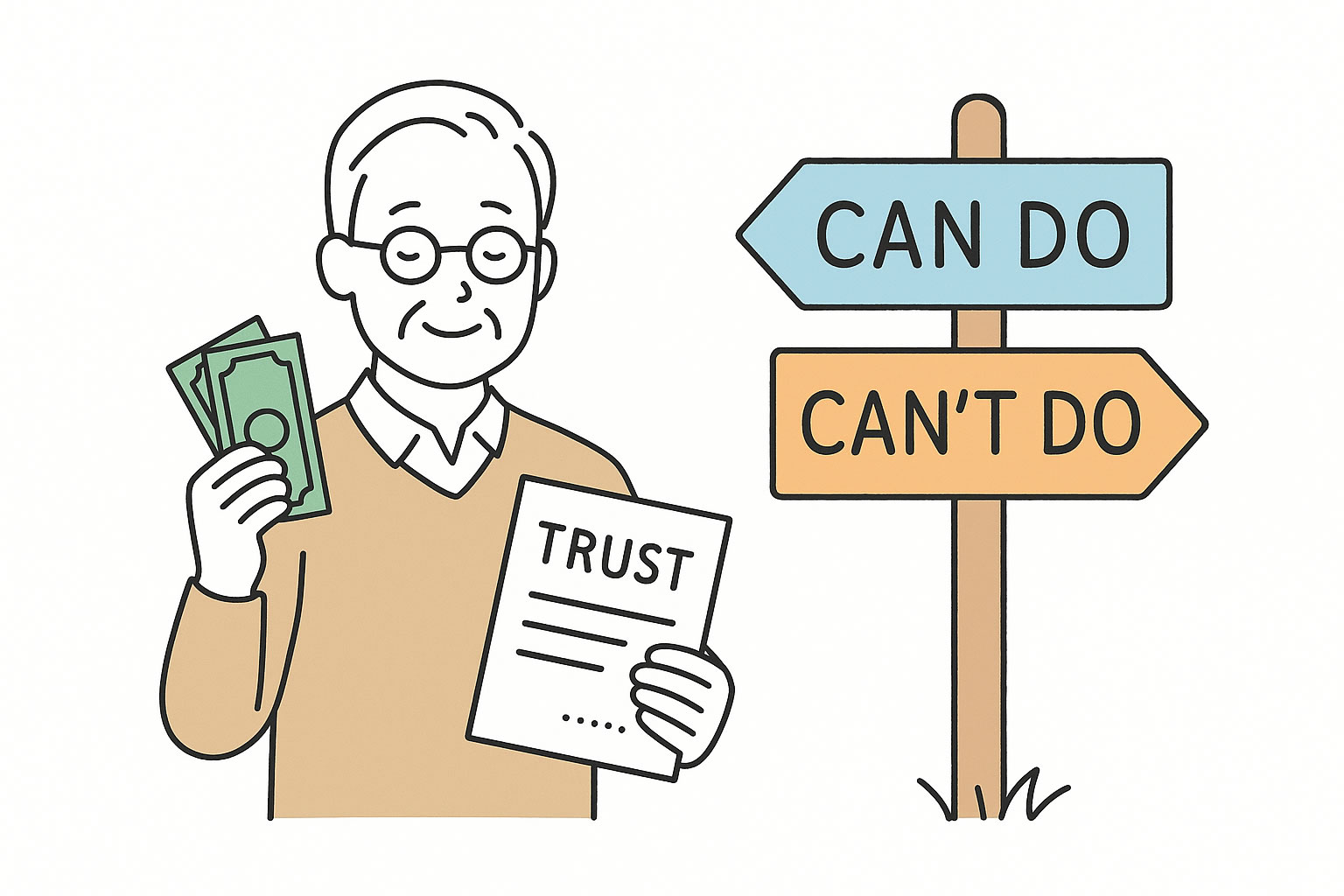家族信託でできること・できないこと
信託財産で管理・運用できるもの
家族信託で信託できる主な財産は以下のとおりです。
- 不動産: 自宅、賃貸物件、土地など、登記可能なあらゆる不動産を信託できます。賃貸収入を受益者に渡す設計も可能で、認知症などで判断能力が低下しても、受託者が不動産の売却や賃貸、修繕などを継続して行えます。
- 金融資産: 預貯金、有価証券、株式など。ただし、信託口口座の開設が必要となるため、銀行や証券会社の対応を確認する必要があります。すべての金融機関が家族信託に対応しているわけではありません。
- その他動産: 高価な美術品、自動車、船舶なども信託できます。ただし、管理や評価が難しい場合があり、信託契約書に詳細な管理方法を明記する必要があります。
信託でできる代表的なこと
家族信託は、資産管理と承継において柔軟な対応を可能にします。
- 認知症に備えた財産管理: 判断能力が低下しても、あらかじめ指名した受託者が信託財産を管理・運用できるため、本人の意思に沿った財産管理を継続できます。これにより、資産の凍結リスクを回避し、生活費や介護費用を滞りなく確保できます。
- 不動産の売却や賃貸、修繕などの柔軟な対応: 不動産の所有権を受託者に移転することで、所有者が認知症などで判断能力を失った後も、受託者が迅速に不動産取引を行えます。これにより、賃貸物件の入居者募集や修繕、さらには売却といった対応もスムーズに進められます。
- 二次相続(孫世代)までを見据えた承継設計: 「受益者連続型信託」を利用することで、最初の受益者の死亡後、次の受益者(例えば子)に、そのまた次の受益者(例えば孫)にと、複数世代にわたる財産の承継順位や承継方法をあらかじめ指定できます。これにより、遺言では指定できない、先の世代への財産承継も可能です。
- 障がいのある子の生活支援としての信託設計(福祉型信託): 親亡き後の障がいのある子の生活を保障するため、親が財産を信託し、受託者に子の生活費や医療費の管理・交付を委ねることができます。これにより、子が判断能力を失っても、必要な支援を継続的に受けられるようになります。
- 事業承継対策: 自社株式を信託財産とすることで、後継者が円滑に経営権を承継できるよう設計できます。これにより、複数の相続人がいる場合でも、株式が分散することを防ぎ、安定した経営体制を維持できます。
家族信託でできないこと
家族信託には多くのメリットがありますが、できないことも存在します。
- 債務の信託: 借金などの債務は信託財産に含めることができません。信託できるのは「財産」のみです。
- 生命保険契約そのものの信託: 生命保険契約自体を信託することはできません。ただし、保険金が支払われた後の資金を信託財産として管理することは可能です。
- 金融機関によっては預金の信託に非対応: すべての金融機関が家族信託に対応しているわけではありません。信託口口座の開設を拒否される場合もあるため、事前に確認が必要です。
- 受益者の不利益になる契約の強行(利益相反行為): 受託者は受益者のために行動する義務があるため、受託者自身の利益のために受益者に不利益となる契約(例えば、信託財産を安く買い取るなど)を行うことはできません。
- 公的な手続きの代行: 住民票の取得、年金受給手続き、介護保険申請など、本人の一身専属的な公的手続きを代行することはできません。これらは、成年後見制度の利用などを検討する必要があります。
- 税金対策: 家族信託は基本的に相続税や贈与税などの税金対策にはなりません。財産の移転があったとみなされるため、通常の相続や贈与と同様に課税対象となります。
相続と異なる制約・注意点
家族信託は遺言や成年後見制度とは異なる特性を持つため、特有の制約や注意点があります。
- 相続と違い、契約内容が優先されるため、自由度は高いが設計ミスがトラブルに直結: 家族信託は当事者間の契約に基づいて効力を持つため、契約内容に不備があると、後々大きなトラブルに発展する可能性があります。専門家と協力し、慎重な設計が求められます。
- 遺留分減殺請求の対象になる場合がある: 家族信託によって特定の相続人への財産集中が起こる場合、他の相続人が持つ「遺留分」(最低限保障される相続財産の割合)を侵害する可能性があります。その場合、遺留分減殺請求の対象となることがあります。
- 受託者の行動に第三者が異議を唱えにくく、信頼関係が崩れると問題が長期化: 受託者の権限は強いため、受託者と委託者・受益者間の信頼関係が非常に重要です。信頼関係が崩れると、受託者の不正行為などに対するチェックが働きにくく、問題が長期化するリスクがあります。
- 信託契約の変更・解除が難しい場合がある: 一度締結した信託契約は、原則として契約当事者全員の合意がないと変更・解除ができません。将来の状況変化に対応できるよう、柔軟性を持たせた設計が重要です。
- 税務上の手続きが複雑: 家族信託を組成した場合、税務上の申告や手続きが必要になる場合があります。特に、不動産や有価証券を信託財産とする場合は、税理士など専門家のアドバイスが不可欠です。
最後に
いかがでしたでしょうか。家族信託は非常に柔軟な制度ですが、その分、専門的な知識と慎重な設計が求められます。ご自身の状況に合わせて、専門家にご相談いただくことをお勧めします。