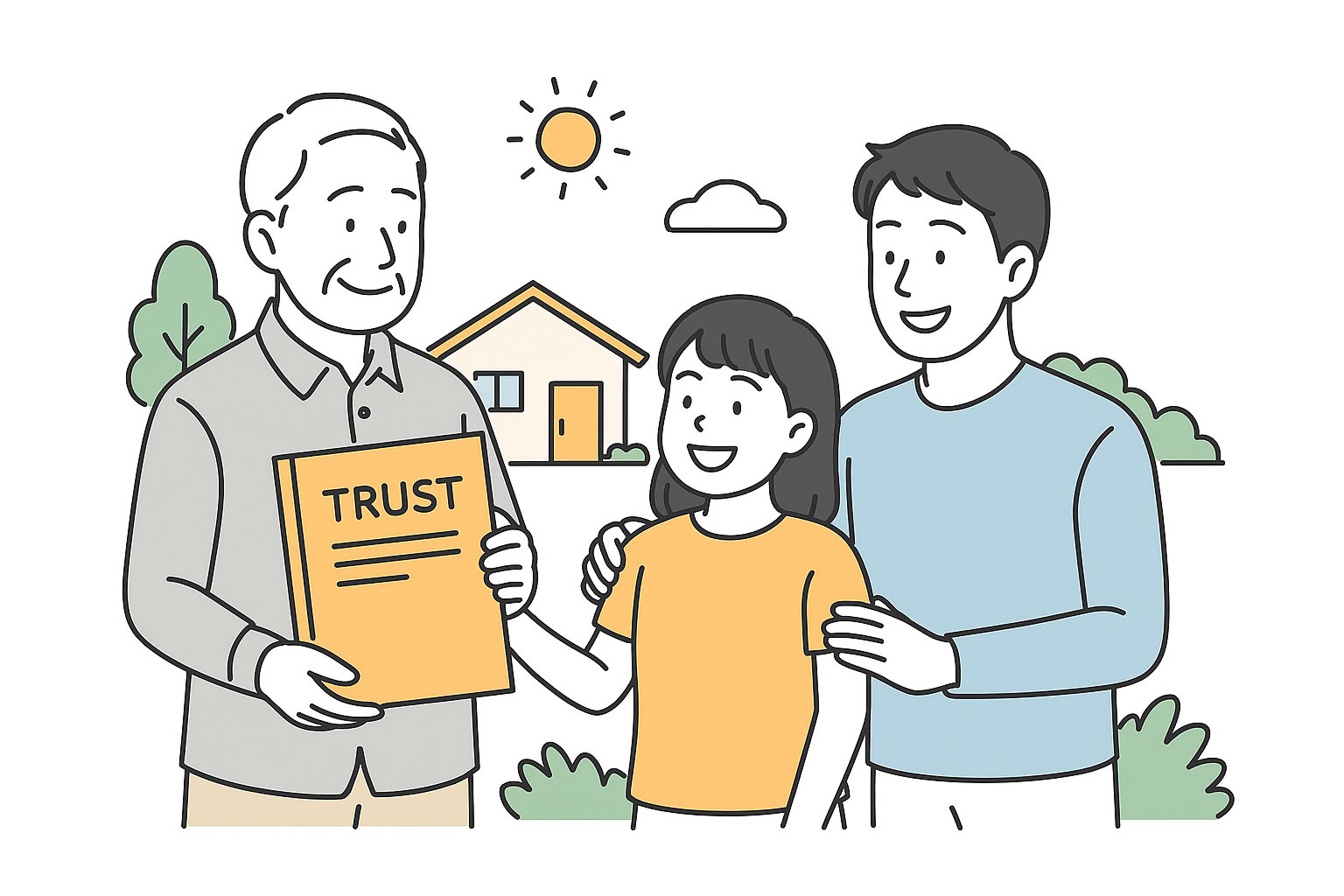はじめに:家族信託とは?
家族信託の基本概念と目的
家族信託とは、ご自身の財産(不動産、預貯金、有価証券など)を信頼できるご家族に託し、あらかじめ定めた目的に従って、特定の人のために管理・処分・承継する財産管理手法です。特に、高齢化社会において深刻化する「認知症による資産凍結」を防ぐ仕組みとして、その有効性が広く認識されています。
この制度の根幹は、財産の「管理・運用する権利」と「そこから利益を受ける権利」を分離することにあります。具体的には、財産を託す人である「委託者」が、信頼できるご家族である「受託者」に財産を移し、受託者は「受益者」のためにその財産を管理・運用します。典型的な家族信託の構成としては、親が委託者となり、子が受託者、そして親自身が受益者となる「自益信託」の形が一般的です。これにより、受託者である子が親の財産を親のために管理する制度が実現します。
信託には、信託銀行などが報酬を得て行う「商事信託」と、ご家族などが報酬を得ずに行う「民事信託」の二種類があります。家族信託はこの「民事信託」に分類され、信託業法の制限を受けずにご家族が受託者となることが可能です。この仕組みにより、委託者が認知症などで判断能力が低下した場合でも、信託の目的に応じてご自身の財産を柔軟に活用し、生活費や医療・介護費用を滞りなく確保できるようになります。
なぜ今、家族信託が注目されるのか
日本は世界でも有数の長寿社会であり、それに伴い認知症患者の増加が社会全体で喫緊の課題となっています。厚生労働省の推計によれば、2025年には65歳以上の高齢者の約20%、およそ700万人が認知症高齢者になると予測されており、これはもはや他人事ではありません。
認知症を発症すると、財産の名義人であるご本人の判断能力が低下したとみなされ、銀行口座が凍結されたり、不動産の売却や管理が困難になったりするリスクが生じます。口座が凍結されると、ご本人の生活費や医療・介護費用の引き出しもできなくなり、ご家族が一時的に費用を肩代わりするといった経済的な負担が生じる可能性もあります。このような状況は、ご本人だけでなくご家族の生活にも大きな影響を及ぼしかねません。
従来の財産管理や承継の制度、例えば遺言や成年後見制度だけでは、こうした現代社会の新たなニーズに十分に応えきれない側面がありました。遺言はご本人の死後の財産承継に特化しており、生前の柔軟な財産管理には対応できません。また、成年後見制度はご本人の財産保護に重点を置くため、積極的な資産運用や迅速な資金捻出には不向きです。
家族信託の台頭は、単なる法制度の進化に留まらず、社会の高齢化という大きな流れが、個人の生活設計やご家族の関係性に具体的な影響を与え、それに対応する新たな「社会インフラ」としての財産管理手法が求められていることを示唆しています。特に、家族信託が「民事信託」として、家庭裁判所の介入を最小限に抑え、ご家族間の信頼関係を基盤としている点は、プライバシーを重視し、より家庭内で完結する解決策を求める現代のニーズに合致していると言えるでしょう。これは、国家による「保護」から、ご家族による「自己管理・自己責任」へと、財産管理のあり方が変化しつつある兆候とも解釈できます。このような背景から、ご本人の意思を尊重しつつ、ご家族が主体的に財産を管理・承継できる家族信託が、今、大きな注目を集めているのです。
第1章:家族信託の「登場人物」と「仕組み」を理解する
委託者、受託者、受益者とは?(役割と関係性を図解で解説)
家族信託を理解する上で、まず把握すべきは、この制度を構成する主要な三者の役割と、その間の関係性です。信託は、財産を託す「委託者」、信託された財産を管理・運用する「受託者」、そして信託された財産から生じる利益を受け取る「受益者」の三者によって成り立っています。
- 委託者(いたくしゃ)
- 役割: ご自身の財産を信託する人であり、家族信託の契約を始める起点となる人物です。信託する財産の種類や範囲、信託の目的、そして誰を受益者とするかなど、信託の基本的な枠組みと運用方針を決定します。
- 家族信託における典型例: 財産の所有者である親御様や、将来の認知症に備えたいご本人などがこの役割を担います。
- 重要な点: 家族信託は契約行為であるため、委託者には契約締結時に十分な判断能力が求められます。
- 受託者(じゅたくしゃ)
- 役割: 委託者から信託された財産を預かり、信託の目的に従って、受益者のためにその財産を管理・運用・処分する人です。受託者は、信託財産から得られた利益を受益者に交付する義務を負います。
- 家族信託における典型例: 委託者が最も信頼できるご家族(お子様など)が選ばれることが一般的です。ご家族以外でも、信頼関係があれば遠縁の親族、友人、知人なども受託者となることができます。
- 重要な義務と責任: 受託者には、信託法によって「善管注意義務(善良な管理者の注意義務)」、「忠実義務(受益者のために誠実に職務を行う義務)」、「分別管理義務(信託財産と自身の固有財産を明確に区別して管理する義務)」、「帳簿等の作成・報告・保存義務」など、多くの法的義務と重い責任が課せられます。これらの義務を怠ると、受託者は損害賠償責任を負う可能性もあります。
- 受益者(じゅえきしゃ)
- 役割: 信託された財産から生じる利益を享受する人です。この利益を受け取る権利は「受益権」と呼ばれ、受益者はこの権利を行使して、受託者に対し信託財産の管理状況の報告を求めたり、受託者を解任したりする権限を持ちます。
- 家族信託における典型例: 契約当初は、委託者自身が受益者を兼ねるケースがほとんどです(「自益信託」)。委託者兼受益者が亡くなった後、受益権を配偶者や子などが引き継ぐケースもあります。
- 重要な点: 受益者は、信託財産の実質的な所有者とみなされ、信託期間中の財産から生じる収益に対して課税されます。
これらの三者がそれぞれの役割を果たすことで、家族信託はご本人の意思を未来に繋ぎ、財産を円滑に管理・承継する仕組みとして機能します。
【家族信託の登場人物(委託者・受託者・受益者)の役割と関係性】
| 登場人物 | 役割 | 主な行動・責任 | 家族信託における典型例 |
| 委託者 | 財産を託す人 | ・信託の目的、対象財産、受益者を決定する ・信託契約を締結する(判断能力が必要) | ・親、高齢者ご本人 |
| 受託者 | 財産を預かり管理・運用する人 | ・信託目的に従い、受益者のために財産を管理・運用・処分する ・帳簿作成、報告など法的義務を負う | ・子、信頼できる親族 |
| 受益者 | 信託財産から利益を受け取る人 | ・信託財産から生じる収益を受け取る ・受託者の財産管理状況を監督する権利を持つ | ・親(委託者と同一)、配偶者、子、孫 |
第2章:家族信託を始める「きっかけ」と「おすすめのケース」
家族信託を検討する最適なタイミング
家族信託は、ご本人の判断能力が十分にあるうちに契約を締結することが不可欠な制度です。認知症の症状が進み、ご本人の意思能力が確認できなくなると、家族信託の契約を結ぶことは困難になります。そのため、将来のリスクに備えるためには、早めの検討が推奨されます。
一般的に、50代から60代は家族信託の検討を始める最適なタイミングとされています。この時期は、親御様がまだお元気なうちに、ご家族で財産管理や相続に関する意向をじっくりと話し合い、信託契約の内容を具体的に決めていくことができます。また、配偶者やお子様に対する財産移転の準備としても活用でき、将来の生活設計を見据えた財産管理が可能になります。
もちろん、認知症の発症リスクは年齢とともに高まりますが、脳梗塞や事故など、年齢に関わらず突然判断能力を失う可能性も否定できません。そのため、財産管理を次世代に早めに任せたいという明確な意思がある場合は、比較的若いうちから検討することも選択肢の一つです。ご家族の状況や財産の種類、将来の希望を総合的に考慮し、専門家と相談しながら最適なタイミングを見極めることが重要です。
具体的な活用事例と、家族信託が「おすすめ」されるケース
家族信託は、その柔軟性から多岐にわたるご家族のニーズに対応できる点が大きな特徴です。ここでは、特に家族信託が有効に活用される具体的なケースをご紹介します。
ケース1:認知症による資産凍結対策
ご本人が認知症を発症し、判断能力が低下すると、ご自身の銀行口座が凍結され、生活費や医療・介護費用が引き出せなくなる可能性があります。また、ご自宅や貸しビルなどの不動産を所有している場合でも、ご本人が契約行為を行えなくなるため、売却や賃貸、大規模修繕などができなくなり、資産が「塩漬け」状態になるリスクがあります。
家族信託による解決: ご本人がお元気なうちに家族信託契約を締結し、信頼できるお子様などを受託者として不動産や金銭を信託財産とすることで、ご本人が認知症になった後も、受託者がご本人のために財産を管理・運用・処分することが可能になります。例えば、介護施設への入居費用を捻出するためにご自宅を売却する必要が生じた場合でも、受託者がご本人に代わって売却手続きを進め、その資金を介護費用に充てることができます。成年後見制度のように家庭裁判所の許可や後見人への報酬支払いが不要なため、より柔軟かつ迅速な対応が実現します。
ケース2:障害を持つ子どもの将来支援(親なきあと問題)
知的障害や精神障害などにより、判断能力に課題があるお子様がいらっしゃる場合、親御様はご自身が亡くなった後や高齢になった際の、お子様の生活や財産管理について大きな不安を抱えることがあります。これは「親なきあと問題」と呼ばれています。
家族信託による解決: 親御様が委託者となり、信頼できる兄弟姉妹や親族を受託者、障害を持つお子様を受益者として家族信託を設定することで、親御様が亡くなった後も、受託者が信託財産を管理し、お子様の生活費や医療費、福祉サービス費などを継続的に支払い続けることが可能になります。信託契約に「毎月の生活費として〇万円まで」「医療費や介護費は必要に応じて支出可能」といった具体的な支出ルールを定めておくことで、受託者が迷わずに管理でき、透明性のある運用が実現します。これにより、親御様がいなくなっても、障害を持つお子様が安心して生活できる基盤を築くことができます。
ケース3:柔軟な財産管理・運用を実現したい場合
従来の成年後見制度では、ご本人の財産を保全することが主目的であるため、積極的な資産運用やリスクを伴う取引は原則として認められていません。例えば、老朽化した収益不動産の建て替えや、新たな不動産投資などは、成年後見制度では難しいのが実情です。
家族信託による解決: 家族信託では、信託契約の内容にご本人の希望や方針、それに伴う受託者の権限を詳細に記載できるため、受託者はご本人の意思に沿った柔軟な財産管理や積極的な資産活用を行うことができます。例えば、投資用不動産を信託財産とし、受託者であるお子様に物件の管理や入居者対応、さらには売却・買い替え、新規アパート建設などの権限を与えることで、親御様の判断能力が低下した後も、ご家族主導で収益不動産を継続的に管理・運用し、相続税対策を進めることが可能になります。
ケース4:不動産の共有トラブル回避
ご家族で不動産を共有名義にしている場合、共有者の誰か一人でも認知症などで判断能力を欠くと、その不動産の売却や建て替え、大規模修繕といった共有者全員の同意が必要な行為ができなくなるという問題が生じます。これにより、不動産が有効活用できず、結果的にご家族間のトラブルに発展する可能性があります。
家族信託による解決: 家族信託を利用して、共有不動産の管理権限を信頼できる一人の受託者に集約することで、これらのリスクを回避し、不動産の管理・運用をスムーズに行うことができます。受託者は信託契約に基づき、単独で不動産の売却や賃貸、修繕などの意思決定を行えるため、共有者全員の合意が得られなくなる事態を防ぎ、財産の有効活用を継続できます。
ケース5:事業承継対策
ご自身が会社経営者である場合、将来、認知症などで判断能力が低下した際に、会社の株式や経営に関わる不動産の管理・承継が滞り、事業の継続性に影響が出ることを懸念されることがあります。また、複数の相続人に株式が分散することで、経営権が不安定になるリスクも存在します。
家族信託による解決: 家族信託を活用することで、オーナー社長の認知症に備えた事業承継対策が可能です。例えば、ご自身の会社株式や事業用不動産を信託財産とし、後継者となるお子様などを受託者に指定することで、オーナー社長の判断能力に関わらず、受託者によって議決権行使や事業資産の管理がスムーズに行えるようになります。これにより、事業の継続性を確保し、円滑な世代交代を実現できます。特定の相続人に株式を引き継ぎ、別の相続人に不動産を引き継ぐといった、財産分配の調整にも活用できます。
ケース6:二次相続以降の指定(受益者連続型信託)
遺言書では、ご本人の死後の財産承継先(一次相続)は指定できますが、その財産を受け継いだ相続人が亡くなった後の承継先(二次相続以降)を定めることはできません。このため、ご自身の財産を「孫の代まで確実に承継させたい」といった希望があっても、従来の制度では実現が困難でした。
家族信託による解決: 家族信託の大きな特徴の一つに、「受益者連続型信託」という機能があります。これは、配偶者や子への一次相続だけでなく、孫やひ孫といった複数世代にわたる相続についても、信託契約内で承継先をあらかじめ指定できる仕組みです。例えば、「まずは妻に、妻の死亡後は長男に、長男の死亡後は孫に」といったように、ご自身の希望する順番で何段階にも資産承継者を指定できます。これにより、ご本人の意思を長期にわたり財産に反映させ、代々受け継がれる資産を確実に次世代へと繋ぐことが可能になります。
家族信託の多様な活用事例は、その「柔軟性」と「目的適合性」を明確に示しています。この制度は、認知症対策や多世代承継など、従来の制度では実現困難な多くのニーズに対応できることが示されています。これに対し、成年後見制度は財産保全が主目的であり、積極的な運用や多世代承継には不向きです。遺言も一次相続のみに限定されます。家族信託の契約内容は、ご本人の具体的な意向やご家族の状況に合わせて「オーダーメイド」で設計できる点が、他の既存制度では実現が困難な「柔軟性」を生み出しています。この柔軟性こそが、現代社会の多様化する財産管理・承継ニーズに合致し、多くのケースで最適な解決策となり得る理由です。この「柔軟性」は、単に多くの問題に対応できるというだけでなく、個々の家族が持つデリケートな事情や、長期的な未来を見据えた複雑な計画(例えば、事業の継続性や特定の家族への継続的な支援)を、法的に担保された形で実現できることを意味します。これは、画一的な制度では対応しきれない、現代社会における「個別最適化」への強い要求が、法制度の進化を促している一つの表れです。家族信託は、単なる財産管理ツールではなく、ご家族の絆や価値観を次世代に継承するための「意思の器」としての役割も担っていると言えるでしょう。
家族信託が「必要ない」ケース
家族信託は非常に有用な制度ですが、すべてのご家庭に万能な解決策ではありません。以下のようなケースでは、家族信託の必要性が低い、あるいは適さない可能性があります。
- 預貯金が少なく不動産を持っていない場合
- 家族信託の契約には、専門家への報酬や公正証書の作成費用など、数十万円単位の初期費用がかかります。財産が少ない場合、この費用が負担となり、本来得られるはずのメリットが薄れてしまう可能性があります。また、農地を信託財産とする場合は農地法の許可が必要ですが、許可が下りることはほとんどありません。預貯金の管理が主な目的であれば、銀行が提供する代理人制度など、より簡便な方法で対応できる場合もあります。
- すでに生前贈与で資産移転を済ませている方
- すでに財産が生前贈与によってお子様やお孫様の名義になっている場合、改めて家族信託を設定する必要性は低いと考えられます。ご本人が認知症になったり急な出費が必要になったりしても、贈与された財産を使って対応できるためです。生前贈与は、年間110万円の基礎控除額を利用して計画的に行われることが多いです。
- ご本人が若く認知症リスクが低い状況
- ご本人が40代や50代など比較的若く、健康上の問題がない場合、認知症の発症リスクは低いと判断され、家族信託はまだ時期尚早と考えることもできます。家族信託契約後は、預貯金や不動産の名義が受託者に変更されるため、ご本人がご自身の財産を自由に使う際に、毎回受託者を通す手間が発生する可能性があります。ただし、認知症に限らず、脳梗塞や事故などで突然判断能力を失う可能性は誰にでもあります。将来に備えて財産管理を次世代に早めに任せたいという明確な意思がある場合は、若いうちから検討することも有効な選択肢となります。
- ご家族間の信頼関係に問題がある場合
- 家族信託は、ご家族や親族間の「信頼」が何よりも前提となる制度です。委託者と受託者間で契約が締結されるため、他の親族が契約内容を知らずに誤解したり、受託者が財産を私的に使い込むのではといった疑念を抱かれたりするなど、親族間の関係が悪化するおそれがあります。受託者以外に相続人がいる場合、相続時にトラブルになる可能性も否定できません。このようなトラブルを防ぐためには、家族信託を行う目的や詳細を事前に親族全員に伝え、十分な話し合いと合意形成を行うことが不可欠です。ご家族間の信頼関係がすでに損なわれている場合は、家族信託の利用は慎重に検討すべきであり、成年後見制度など、家庭裁判所が監督する制度の利用が適している場合もあります。
第3章:家族信託の「メリット」と「デメリット」
家族信託は、ご家族の財産管理と承継において多くの利点をもたらす一方で、いくつかの注意すべき点や課題も存在します。制度の利用を検討する際は、これらのメリットとデメリットを総合的に理解することが重要です。
家族信託の8つのメリット
- 認知症による資産凍結に備えられる 家族信託を設定すると、委託者(財産を託す人)の財産の所有権が形式的に受託者(財産を管理する人)に移転するため、委託者の判断能力の有無に関わらず、信託財産(金銭、不動産、有価証券など)の管理・運用・処分が可能になります。これにより、ご本人が認知症を発症しても銀行口座の凍結や不動産の売却不能といった事態を回避し、ご本人の生活費や医療・介護費を滞りなく支えることができます。
- 成年後見制度では難しい柔軟な財産管理が実現できる 成年後見制度はご本人の財産保全が基本であり、財産が減る行為や積極的な資産運用は原則として認められません。これに対し、家族信託では家庭裁判所の関与なしに、信託契約で定めた範囲内で、より柔軟な財産管理や運用が可能です。例えば、収益不動産の建て替えや買い替え、株式投資など、ご本人の意思に沿った多様な資産活用が実現できます。
- 遺言としての機能も果たす 家族信託契約書内で、委託者死亡後の信託財産の承継先を定めることができます(遺言代用型信託)。これにより、信託財産については遺産分割協議を行う必要がなくなり、ご本人の意思を確実に反映した財産承継が可能です。家族信託は遺言よりも効力が高く、仮に遺言書と内容が競合しても家族信託が優先されます。
- 不動産の共有によるリスクを回避できる 共有名義の不動産がある場合、共有者の誰か一人でも認知症などで判断能力を欠くと、売却や建て替え、大規模修繕といった共有者全員の同意が必要な行為ができなくなります。家族信託で管理権限を受託者に一本化することで、これらのリスクを回避し、不動産の管理・運用をスムーズに行うことができます。
- 相続時の負担が軽減される 家族信託契約内で財産の承継者やその内容を適切に定めておくことで、委託者に相続が発生した際に遺産分割協議が不要となり、相続人の負担を軽減できます。相続人が認知症の場合でも、成年後見制度の利用なしに手続きを進められるため、ご家族間の争いを未然に防ぐ効果も期待できます。
- 倒産隔離機能がある 信託された財産は、委託者や受託者が将来的に破産したり、信託財産に関係のない債務を負ったりしても、その影響を受けず守られる「倒産隔離機能」を有します。信託財産は独立した財産として扱われるため、破産や債務の差押え対象になりません。
- 二次相続以降についても定められる 家族信託では、配偶者や子への一次相続だけでなく、孫やひ孫といった複数世代にわたる相続についても定めることができます(受益者連続型信託)。これにより、遺言では指定できない先の世代への財産承継が可能となり、ご本人の望む相続計画をより具体的に実現できます。
- 事業承継対策もできる 自社株式を信託することで、オーナー社長の認知症に備えた事業承継対策が可能です。後継者を受託者とすれば、オーナー社長の判断能力に関わらず、受託者によって議決権行使が可能となり、事業の継続性を確保できます。
家族信託のデメリットと注意点
- 直接的な節税対策にはならない 家族信託を設定しても、相続税や贈与税の直接的な節税効果は期待できません。信託財産からの収益は受益者に対して課税され、受益者が受け取る財産は「みなし相続財産」として相続税の対象となることに変わりはありません。節税が最優先の目的であれば、家族信託は必ずしも適切ではない可能性があります。
- 受託者の負担が大きい 財産の管理・運用業務を担う受託者には、信託法で多くの義務が定められており、その負担は決して小さくありません。特に、帳簿作成や税務署への書類提出など、長期間にわたる事務作業が発生する可能性があります。この負担から、受託者を引き受けてくれるご家族が見つからない場合や、途中で辞任を申し出るケースも起こり得ます。
- 受託者の裁量が大きく、横領のリスクもゼロではない 受託者は委託者の大切な財産を直接管理するため、法律で義務が定められているとはいえ、万が一、受託者が横領などの契約違反を起こす可能性はゼロではありません。このようなリスクを防ぐためには、家族信託契約に詳細な規定を設け、公正証書で締結すること、そして信託監督人や受益者代理人を設定して受託者の事務を監督する仕組みを導入することが有効です。
- 「身上監護」には対応していない 家族信託は財産管理の契約であり、ご本人の生活や医療、介護に関する契約手続き(例えば、介護施設の入退所契約や入院手続きなど)を行う「身上監護」の権限は含まれません。これらの手続きが必要な場合は、成年後見制度や任意後見制度を併用することで補完することが可能です。
- 信託できない財産もある 預金債権(銀行口座そのもの)や年金受給権などの一身専属権、農地などは信託できません。金銭を信託する場合は「金〇〇円」という具体的な金額で設定し、年金は受給口座から信託用口座に移すことで金銭として信託可能です。
- 遺留分侵害額請求を受ける可能性がある 法定相続人(配偶者・子・父母)には、法律で最低限保証された相続分である「遺留分」があります。家族信託の内容がこの遺留分を侵害する場合、遺留分にあたる金額を請求される可能性があります。トラブルを避けるためには、相続人となる可能性のあるご家族全員と事前に話し合い、合意を得ることが重要です。
- 認知症になる前の対策が必要 家族信託は契約行為であるため、契約締結時には委託者と受託者の判断能力が必要です。ご本人の認知症が進み、判断能力が確認できない場合は、家族信託契約を結ぶことはできません。物忘れの症状があっても判断能力が確認できれば契約は可能ですが、不安がある場合は早めに専門家に相談することが推奨されます。
- 損益通算ができないリスク 信託財産に収益不動産がある場合、そこから生じる不動産所得の損失は、信託財産以外の所得と損益通算することができません。また、純損失の繰り越しもできないため、税務上の不利益が生じないか、税理士などの専門家に相談して十分に検討する必要があります。
- 税務申告の手間が増す 家族信託を設定すると、税務署への届出や毎年の税務申告の手間が発生する場合があります。例えば、信託設定時や信託財産から年間3万円を超える収益がある場合、受託者は信託財産に関する調書や計算書を税務署に提出する義務があります。収益不動産がある場合は、受益者が確定申告書に不動産所得用の明細書と信託財産に関する明細書を添付する必要があります。
- 長期間、当事者を拘束する可能性 家族信託は二次相続以降の指定も可能なため、信託契約の期間が長期に及ぶことがあります。20年、30年と契約が続くうちに、ご家族の環境や状況が変化し、ご家族間の信頼関係が変化するリスクも存在します。特に、長期間の拘束により受託者の負担が強まったり、体調を崩して継続できなくなるリスクも見越した契約設計が必要です。
- 家族信託を熟知した専門家が少ない 家族信託は比較的新しい制度であり、その複雑性から、広範囲な専門知識と実務経験を持つ専門家はまだ限られているのが実情です。個々のご家族に適した設計を行うには、法律、税金、登記、不動産管理などに関する幅広い知識と経験が求められます。専門家選びは、家族信託の成否を左右する重要な要素となります。
- 初期費用がかかる 家族信託には、専門家への報酬、公正証書の作成費用、不動産登記に関わる費用、登録免許税などの諸費用が発生します。専門家にすべてを依頼する場合、数十万円から100万円程度かかることが一般的です。費用対効果を考慮し、事前に見積もりを確認することが重要です。
- 信託口口座を作れない場合がある 金銭を信託財産とする場合、受託者個人の財産と分離して安全に管理するために、信託専用の銀行口座(信託口口座)の開設が推奨されます。しかし、日本全国すべての銀行で信託口口座の開設に対応しているわけではなく、金融機関によっては最低預け入れ額が設定されている場合や、公正証書の提示が条件となることもあります。
- 親族間で不公平感・トラブルが発生する可能性 受託者に財産管理の権限が集中するため、他の相続人から理解が得られないケースや、不公平感が生まれ、トラブルに発展する可能性があります。特に、同居していないご家族には説明が行き届きにくい傾向があります。家族信託を始める際は、必ず信託契約の当事者以外の親族からも理解を得ることが重要です。
- 30年ルールによる受益権取得の制限 受益者連続型信託の場合、信託契約開始から30年が経過すると、新たな受益権を取得できるのは一度限りとなります。例えば、子が受け継いだ信託財産を、30年経過後に子の死亡によって孫が新たに受益者として受け継いだ場合、孫が死亡すると信託契約は自動的に終了し、それ以上継続することはできません。
家族信託のメリットは、その「柔軟性」と「オーダーメイド性」に起因しますが、この柔軟性が高いがゆえに、契約設計の不備やご家族間の合意形成の欠如が、そのままデメリットとして顕在化するリスクをはらんでいます。特に、受託者への権限集中と、それに対する他のご家族の理解・信頼が不可欠である点が強調されます。信頼関係が前提となる制度であり、これが欠如するとメリットがデメリットに転じる可能性が高いのです。家族信託の成功は、単に法的な手続きの正確さだけでなく、ご家族間の「信頼資本」に大きく依存していることを示しています。この制度は、ご家族が互いの将来を支え合うという倫理的・社会的な側面を強く持ち合わせています。したがって、契約締結前の十分な話し合いと、契約後の透明性のある運用(信託監督人の設定など)が、長期的なご家族関係の維持と財産管理の円滑化に不可欠となります。これは、法制度が社会関係の質に深く影響を与え、またその質によって制度の有効性が左右されるという、社会と法の相互作用を示す好例と言えるでしょう。
第4章:家族信託と他の制度との比較:家族信託が「優れている点」
家族信託は、ご自身の財産管理や承継を考える上で、遺言、成年後見制度、任意後見制度、生前贈与、銀行の代理人制度といった他の選択肢と比較検討されることが多くあります。それぞれの制度には特性があり、家族信託は特定のニーズにおいて顕著な優位性を示します。
家族信託 vs. 遺言
- 遺言の限界: 遺言は、ご本人の死後の財産承継先(一次相続)を指定する強力な意思表示手段ですが、その効力はご本人の死亡時に発生し、生前の財産管理には利用できません。また、遺言では、財産を受け継いだ相続人が亡くなった後の承継先(二次相続以降)を定めることができないという限界があります。このため、亡くなる順番によっては、ご本人の意図しない人物や外部の家族に財産が渡ってしまう可能性があります。
- 家族信託の優位性: 家族信託は、ご本人の生前から財産管理を開始できる点が大きな優位性です。また、「受益者連続型信託」を利用することで、お子様や配偶者だけでなく、孫やひ孫といった複数世代への相続指定が可能になります。これにより、ご本人はご自身の財産が直系の家族だけでなく、将来の世代にも確実に継承されるよう指定でき、ご本人の望む相続計画をより具体的に実現できます。さらに、家族信託は遺言の代わりとしての効力を持ち、遺言よりも優先して適用されるという特徴があります。遺言が民法で定められた厳格な形式と手続きに従う必要があるのに対し、家族信託は信託法という特別法に基づき、より簡易な手続きで死後の財産承継を定めることが可能です。これにより、相続発生時に遺産分割協議を不要にし、スムーズな財産の移転を実現します。
家族信託 vs. 成年後見制度
- 成年後見制度の限界: 成年後見制度の主な目的は、意思決定能力を失ったご本人の財産を保護し、生活を支援することにあります。この制度では、成年後見人がご本人に代わって財産を管理しますが、主に生活維持のための支出に限られ、財産を減らさないことが基本方針であるため、積極的な資産運用や組み換えは困難です。また、成年後見人の選任には家庭裁判所の関与が必要であり、一度選任されるとご本人の判断能力が回復しない限り、原則としてご本人が亡くなるまで継続し、後見人への報酬も発生します。
- 家族信託の優位性: 家族信託では、信託契約に基づき、管理方法を自由に定めることができます。これにより、不動産の購入や株式投資といった、リスクを伴う資産運用も可能になります。家族信託は、委託者の意向に沿った多様な財産管理を実現し、判断能力が低下した後も、その意思に基づいた財産運用を継続できるのです。また、認知症による資産凍結を回避できる点が大きなメリットです。家族信託を利用すれば、受託者(多くの場合、信頼できるご家族)が委託者(親など)に代わって財産を管理できるため、認知症発症後も円滑な資産運用が可能になります。ご家族が受託者となる場合、原則として報酬は発生せず、家庭裁判所の監督も受けないため、手続きが簡便で、ご家族の意思が反映されやすいという利点もあります。
家族信託 vs. 任意後見制度
- 任意後見制度の限界: 任意後見制度は、ご本人が将来の判断能力低下に備え、あらかじめご自身で任意後見人を選任し、財産管理や身上監護を委任する契約です。その効力はご本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が任意後見監督人を選任して初めて発生します。任意後見人は身上監護(介護や医療契約など)に対応できますが、財産管理においては、家庭裁判所の監督下にあるため、家族信託ほど積極的な運用は難しい場合があります。
- 家族信託の優位性: 家族信託は、契約締結と同時に効力が発生し、ご本人の判断能力が低下する前から財産管理を開始できる点が異なります。また、受託者は裁判所の監督を受けずに、信託契約の範囲内で柔軟かつ積極的に財産管理を行うことが可能です。
- 併用の可能性: 家族信託は財産管理に特化しており身上監護の権限を持たないため、ご本人の生活や療養看護の支援が必要な場合は、家族信託と任意後見制度を併用することが、より包括的な対策となります。家族信託で財産管理の柔軟性を確保し、任意後見制度で身上監護をカバーすることで、ご本人の未来を多角的に守ることが可能になります。
家族信託 vs. 生前贈与
- 生前贈与の限界: 生前贈与は、ご本人が生きている間に財産を子や孫などの他者に贈与する制度であり、相続税の軽減を目的として行われることが多いです。しかし、贈与税や不動産取得税が発生する可能性がある点に注意が必要です。また、贈与された財産は受贈者の固有財産となるため、ご本人の意思とは異なる目的で使われるリスクも存在します。
- 家族信託の優位性: 家族信託は、信託契約を結んだ時点では、実質的な財産権の移転がないため、原則として贈与税や不動産取得税は発生しません(自益信託の場合)。財産の所有権と利益を受ける権利を分離することで、ご本人が引き続き財産からの利益を受け取りながら、管理権限のみを信頼できるご家族に託すことができます。これにより、相続税対策よりも財産管理の柔軟性を重視する場合に、家族信託が適していると言えます。
家族信託 vs. 銀行の代理人制度
- 銀行の代理人制度の限界: 銀行が提供する代理人制度は、主に預貯金の管理に特化しており、代理人による預金の引き出しを可能にするものです。しかし、その適用範囲は預貯金に限られることが多く、不動産の売買や積極的な資産運用はできません。また、ご本人の判断能力が低下し口座が凍結された場合、家族信託のように受託者が自由に引き出すことはできず、成年後見制度の利用が必要となる場合があります。
- 家族信託の優位性: 家族信託は、不動産や有価証券など、より広範な財産を信託財産とすることができ、あらかじめ契約で定めた範囲で柔軟な財産管理が可能です。特に、認知症発症後の口座凍結を回避し、信託口口座を通じて受託者がご本人のために預貯金を引き出し、利用できる点は大きなメリットです。
これらの制度は互いに排他的ではなく、むしろ「補完関係」にあることが示唆されます。例えば、家族信託で財産管理を柔軟に行いつつ、身上監護のニーズには任意後見制度を併用するといった「ハイブリッド型」の対策が、個々の状況に応じた最適な解決策となり得ます。これは、単一の制度がすべての課題を解決できるわけではなく、複数の制度の長所を組み合わせることで、より包括的で堅牢な未来設計が可能になるという理解を深めます。財産管理と未来設計は、個人のライフステージ、ご家族構成、資産状況、そして将来の不確実性(認知症の発症など)によって複雑に変化します。そのため、単一の「完璧な」制度は存在せず、それぞれの制度が持つ特性(強みと弱み)を深く理解し、それらを戦略的に組み合わせることで、個人の「最適解」を導き出す必要性が高まっています。これは、専門家が単なる手続きの代行者ではなく、クライアントの複雑な状況を総合的に分析し、多角的な視点から「コンサルティング」を行う役割の重要性を浮き彫りにします。個々のニーズに合わせたオーダーメイドのソリューションが求められる時代において、専門家の「統合的思考力」がますます価値を持つことを示しています。
第5章:家族信託を始めるための「手続き」と「費用」
家族信託の導入は、ご家族の未来を安心させるための重要なステップですが、その手続きは多岐にわたり、専門的な知識を要します。ここでは、家族信託を始めるための具体的な手続きの流れと、それに伴う費用について詳しく解説します。
家族信託の手続きの流れ(ステップバイステップ)
家族信託は、ご本人の判断能力が十分にあるうちに、ご家族との合意に基づいて進めることが大前提です。公正証書で契約を結ぶ場合、以下のステップで進められます。
- 家族信託の目的と契約内容を家族で話し合う 家族信託を始める上で最も重要な最初のステップは、ご家族全員でその目的と具体的な契約内容について徹底的に話し合うことです。何のために家族信託を利用するのか(認知症対策、空き家対策、相続対策、資産運用、遺言代用信託など)、どの財産を信託するのか、誰を受託者にするのか、受託者の権限の範囲、受益者の権利、信託の終了条件などを明確にします。委託者と受託者の信頼関係が基盤となるため、お互いにしっかりと意思疎通を図り、ご家族全員が納得する形で合意を形成することが、将来のトラブルを防ぐ上で不可欠です。
- 信託契約書を作成する ご家族間の話し合いで決定した内容に基づき、信託契約書の草案を作成します。信託契約書には、信託の目的、信託財産の内容、受託者の義務と権限、受益者の権利、信託の変更・終了事由、財産の帰属先など、必須項目を具体的に記載する必要があります。家族信託は比較的新しい制度であり、契約書の形式も確立されたものではないため、法的効力を持つ適切な契約書を作成するためには、弁護士や司法書士などの専門家に依頼することが強く推奨されます。
- 信託契約書を公正証書にする 作成した信託契約書は、必ずしも公正証書にする必要はありませんが、安心して運用するためには公正証書で作成することが強く推奨されます。公正証書は、公証人が権限に基づいて作成する公文書であり、法的に強い証拠力を有するため、将来のトラブルのリスクを大幅に軽減できます。また、信託口口座を開設する際に、金融機関から公正証書の提示を求められることも多いため、実務上の利便性も高まります。 公正証書の作成は、公証役場に予約を入れ、公証人との面談を経て行われます。当日は、委託者と受託者の本人確認書類(印鑑登録証明書と実印、運転免許証など)を持参し、公証人立ち会いのもと、契約書の内容を確認し署名・捺印を行います。原本は公証役場に20年間保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。
- 信託財産を受託者の名義へ変更する 公正証書による信託契約が完了したら、信託財産の名義を受託者名義に変更する手続きを行います。
- 不動産の場合: 不動産を信託財産に含める場合、法務局で「信託登記」を行います。これにより、不動産の所有権が形式的に受託者に移転し、登記簿謄本にも信託の事実が記載されます。この手続きは司法書士の専門分野です。
- 有価証券の場合: 株式や債券などの有価証券を信託財産に含める場合は、証券会社に信託契約書を提示し、信託内容に基づいた名義変更手続きを行います。
- 金銭の場合: 金銭を信託財産とする場合、後述する信託口口座の開設が必要となります。
- 財産管理のための専用口座(信託口口座)を開設する 金銭を信託財産とする場合、受託者が信託財産を管理するための専用口座である「信託口口座」の開設が非常に重要です。信託口口座は、受託者個人の財産と完全に分離して管理されるため、受託者の破産や死亡時にも信託財産に影響を与えず、口座が凍結される心配がありません。 ただし、信託口口座の開設に対応している金融機関は一部に限られており、金融機関によっては一定の預かり残高が必要な場合や、公正証書で作成された信託契約書が必須となることがあります。口座開設には時間と手間がかかるため、事前に専門家や金融機関に問い合わせ、金融機関の事前審査を受けるなどして、スムーズな手続きを心がけることが推奨されます。
- 家族信託を開始する事務手続きをする 信託契約の締結と財産の名義変更、信託口口座の開設が完了したら、いよいよ家族信託の運用が開始されます。受託者としては、信託口口座への金銭の送金、公共料金の口座振替設定、火災保険の名義変更など、信託財産に関する様々な事務手続きを行う必要があります。また、信託契約書に定めた通り、定期的に信託財産の管理状況を報告書として作成し、受益者や他の関係者に報告することで、信託の透明性が保たれ、ご家族間の信頼を維持することに繋がります。
家族信託の費用相場と内訳
家族信託の費用は、信託財産の種類や金額、ご家族構成、そして依頼する専門家によって大きく異なります。自分で手続きを行う場合と専門家に依頼する場合で費用相場が変わります。
- 自分で家族信託の手続きを行う場合:
- 費用相場は20万円程度とされています。
- 主な内訳は、戸籍謄本や印鑑証明書などの必要書類の取得費用(5,000円~1万円程度)、公正証書の作成費用(5,000円~25万円程度、信託財産の総額による)、信託口口座の開設費用(5万円~10万円程度、金融機関による)、信託契約書に貼付する収入印紙代(200円)です。
- 信託財産に不動産が含まれる場合は、登記事項証明書や固定資産税評価証明書の取得費用(数百円~1,000円程度)に加え、登録免許税(土地:固定資産税評価額の0.3%、建物:0.4%)が発生します。
- ただし、自分で手続きを行うことは、法的・税務的な知識が不足している場合、契約が無効になったり、将来的なトラブルの原因となったりするリスクが非常に高いため、推奨されません。
- 専門家に依頼する場合:
- 費用相場は30万円~100万円程度とされています。
- この費用には、上記の実費に加え、専門家への報酬が含まれます。
- コンサルティング費用: 依頼する専門家によって異なりますが、信託財産の評価額の1.1%程度(最低33万円程度)が目安とされています。信託する財産の範囲を絞ることで費用を抑えることも可能です。
- 信託契約書の作成報酬: 1通あたり約6万円から16.5万円が目安です。
- 信託登記報酬: 不動産がある場合、11万円~16.5万円程度が目安です。
- 公正証書作成代行費用: 公証役場に支払う実費とは別に、専門家への代行報酬として10万円~15万円程度が発生する場合があります。
- 受益者代理人・信託監督人設定費用: これらの役割を専門家に依頼する場合、月額1万円~2万円程度の継続的な費用が発生することもあります。
家族信託は、信託開始時に贈与税や不動産取得税が原則として発生しない「自益信託」が一般的ですが 、信託の設計方法によっては贈与税が課税される「他益信託」となる場合もあります。また、信託期間中に信託財産から生じる所得には所得税が課税され、受益者の死亡時には受益権が相続財産となり相続税の課税対象となります。家族信託自体に直接的な節税効果はほとんどないため、税金面から見ると、最適な設計をしてもプラスマイナスゼロが現実的な評価となります。
家族信託の手続きは多岐にわたり、法律、税務、登記など広範な専門知識が必要とされます。専門家に依頼する場合、数十万円から100万円程度の初期費用がかかることが示されています。しかし、自分で手続きを行うと無効になったり、将来的なトラブルの原因となるリスクが指摘されています。また、信託口口座の開設には公正証書が推奨され、金融機関の事前審査が必要な場合もあります。家族信託の設計と実行には、高度な専門性と正確性が求められます。初期費用は発生するものの、専門家(特に司法書士)に依頼することで、複雑な手続きを円滑に進め、将来的な法的・税務的リスクを回避し、ご家族間のトラブルを未然に防ぐことができます。これは、費用をかけることで得られる「安心」と「確実性」という価値であり、結果的に長期的な視点での「費用対効果」が高いと判断できます。家族信託は「新しい制度」であり、その複雑性から「実務に精通した専門家が少ない」という課題も存在します。この状況は、専門家選びの重要性を一層高めます。単に資格を持つだけでなく、実績、専門性、情報発信力、他士業との連携体制、そして依頼者との相性といった多角的な視点から、真に信頼できる専門家を見極める能力が、家族信託の成功を左右する重要な要素となります。これは、専門サービス市場において、情報の非対称性が高く、消費者が質の高いサービスを見極めるためのリテラシーが求められる現代の課題を反映しています。
第6章:家族信託の「専門家」と「相談先」
家族信託は、法律、税務、登記、金融など多岐にわたる専門知識を要するため、ご自身だけで手続きを進めるのは極めて困難であり、無効になったり将来的なトラブルの原因となったりするリスクが高いです。そのため、信頼できる専門家への相談と依頼が不可欠です。
家族信託を依頼できる専門家とその役割
家族信託の相談先としては、主に以下の専門家や機関が挙げられます。それぞれの専門分野と役割を理解し、ご自身の状況に合った相談先を選ぶことが重要です。
- 司法書士
- 役割: 家族信託の相談窓口として最適な専門家の一つです。不動産登記や信託登記の専門家であり、家族信託の設計から信託契約書の作成、公正証書化、そして信託登記手続きまでをワンストップで対応できます。財産管理・承継の具体的なプランニングや、成年後見制度など他の対策方法との比較検討に関する的確なアドバイスも行います。
- 強み: 成年後見の実績が豊富で、実務経験に優れています。また、ご家族間の意見を調整し、中立の立場でご家族の思いを重視した信託契約書の作成をサポートできる点も大きな強みです。信託口口座開設の7~8割に司法書士が関与しているというデータもあり、その専門性と実務対応能力が評価されています。
- 弁護士
- 役割: 法的トラブルの予防・解決のプロであり、あらゆる法律業務を行うことができます。ご家族間で争いが予想される場合や、すでに紛争が発生している場合、あるいは複雑な資産構成の信託設計が必要な場合に適しています。
- 強み: 紛争解決に強く、将来起こりうる法的リスクを予測した信託契約の設計が可能です。ただし、弁護士が業として受託者になることは信託業法に抵触する可能性があるため、基本的に受託者にはなれません。
- 行政書士
- 役割: 書類作成の専門家であり、信託契約書の作成を依頼できます。
- 注意点: 登記の代理権がないため、不動産の信託登記手続きはご自身で行うか、別途司法書士に依頼する必要があります。
- 税理士
- 役割: 税務・財務面のアドバイスが中心であり、相続税対策の観点から家族信託を提案することがあります。信託設定による税務への影響検討や、不動産収入がある信託の税務処理が必要な場合に相談すべき専門家です。
- 注意点: 法律実務は専門外であるため、法的手続きは他の士業に依頼することになります。
- 金融機関(銀行・信託銀行など)
- 役割: 身近な相談窓口であり、信託口口座の開設や家族信託活用のアドバイス、関連する金融サービスの提供を行っています。
- 注意点: 提供される「家族信託」サービスは「商事信託」であることが多く、財産の種類が限定されたり、柔軟な設計が難しい場合があります。すべての銀行が信託口口座を開設できるわけではなく、専門知識を持つ行員もまだ少ないのが実情です。
- 不動産会社
- 役割: 不動産オーナーが抱える管理や承継の課題に対し、家族信託を提案するケースが増えています。認知症対策と資産凍結防止、不動産の管理・運用・処分、円滑な資産承継、相続対策・節税の提案、次世代オーナーとの連携などが期待できます。
後悔しない専門家選びの「5つの鉄則」
家族信託は比較的新しい制度であり、その複雑性から、信頼できる専門家を選ぶことが成功の鍵となります。以下の「5つの鉄則」を参考に、総合的に判断することが大切です。
- 実績は十分か?「経験値」を見極める 家族信託の案件を実際にどれだけ取り扱ってきたかという「経験値」は非常に重要です。具体的な取扱件数、多様なケースへの対応力、トラブル事例への知見を確認することで、専門家が持つ実務能力の深さを測ることができます。
- 専門性は確かか?「知識の深さ」をチェック 家族信託は奥が深く、関連する法律や税制も改正される可能性があります。専門家が常に最新の知識をアップデートし続けているか、関連資格(例: 家族信託専門士、相続診断士)の保有状況、研修やセミナーへの参加状況などを確認しましょう。また、家族信託ありきではなく、成年後見制度や遺言など、他の制度と比較した上で、ご自身の状況に最適な提案をしてくれるかどうかも重要な判断基準です。
- 情報発信力はあるか? 専門家が持つ知識や家族信託に対する情熱は、その情報発信の量や質にも現れます。ウェブサイトやブログの質と頻度、セミナーや講演の実績、書籍や専門誌への執筆活動、SNSなどでのタイムリーな情報発信を確認することで、その専門分野への真摯な姿勢を測ることができます。
- 連携体制は万全か?他の専門家とのネットワークは? 家族信託は、法律、税務、登記など多岐にわたる分野が絡むため、複数の専門家が連携できる体制が理想的です。税理士、弁護士、行政書士などの他士業、金融機関、不動産関連の専門家とスムーズに連携できるネットワークがあるか、あるいは一つの窓口で多角的なサポートを受けられる「ワンストップサービス」を提供しているかを確認しましょう。
- 相性と信頼感はどうか?客観的な顧客評価を確認 どんなに実績や専門性が高くても、最終的にその専門家と「相性が合うか」「心から信頼して任せられるか」は非常に重要なポイントです。家族信託では、ご家族のデリケートな事情や財産の詳細を伝える必要があるため、話しやすさや真摯な対応は不可欠です。Googleレビューや口コミサイトなどで、実際にその専門家に依頼した人の声を確認することも有効ですが、個別の意見だけでなく、全体的な評価傾向を見ることが大切です。また、契約後も継続的に相談に乗ってくれるか、信託監督などのアフターフォロー体制が充実しているかも確認すべき点です。
家族信託は、法律、税務、登記、金融など多岐にわたる専門知識を要するため、複数の士業や機関が関与する可能性があります。各専門家には得意分野があり、例えば司法書士は登記と契約書作成、弁護士は紛争解決、税理士は税務に強みを持っています。家族信託の成功には、専門家の「実績」「専門性」「連携体制」「情報発信力」「相性・信頼感」が重要であるとされています。家族信託は「オーダーメイド」の性質が強いため、単一の専門家で全てを完結させるのは難しい場合があり、複数の専門家が連携する「ワンストップサービス」の提供が理想的です。依頼者は、ご自身のニーズ(例:不動産が中心か、紛争リスクがあるか、税務対策を重視するか)に応じて、主軸となる専門家を選定し、その専門家が他の分野の専門家と円滑に連携できる体制を持っているかを見極めることが、最適な家族信託を実現するための「戦略的視点」となります。現代の複雑な社会問題(高齢化、多様なご家族形態、資産の多様化)に対応するためには、専門家も従来の「縦割り」ではなく、「横断的」な知識と連携能力が求められています。家族信託の専門家選びは、単に手続きを依頼する行為を超え、ご自身の未来設計を多角的にサポートしてくれる「ライフプランナー」を選ぶ行為に近くなっています。これは、専門家が提供する価値が、単なる技術的サービスから、より包括的な「問題解決コンサルティング」へと進化していることを示しており、依頼者側にもその価値を見極める「目利き」の能力が求められる時代になっていると言えるでしょう。
まとめと結論:家族信託で「安心」と「確実な未来」を築くために
家族信託は、ご自身の財産を信頼できるご家族に託し、ご本人の意思を未来に繋ぐための強力な財産管理・承継手法です。特に、高齢化社会における認知症による資産凍結リスクへの備えとして、その柔軟性と実用性が高く評価されています。
この制度の最大の魅力は、ご本人の判断能力が低下した後も、ご家族がご本人の意向に沿って、預貯金や不動産などの財産を柔軟に管理・運用・処分できる点にあります。従来の成年後見制度では難しかった積極的な資産活用や、遺言では指定できなかった二次相続以降の多世代にわたる財産承継も可能となり、ご家族の多様なニーズに合わせた「オーダーメイド」の財産設計を実現できます。また、不動産の共有トラブル回避や事業承継対策にも有効であり、相続時のご家族の負担軽減にも繋がります。
しかしながら、家族信託は万能な解決策ではありません。受託者には重い法的義務と責任が課せられ、ご家族間の信頼関係が何よりも重要となります。直接的な節税効果はないこと、身上監護の機能を持たないこと、そして契約締結時にはご本人の判断能力が必須であることなど、いくつかのデメリットや注意点も存在します。特に、ご家族間の理解と合意形成を怠ると、かえってトラブルの原因となる可能性も秘めています。
家族信託の成功は、単に法的な手続きの正確さに留まらず、ご家族間の深い信頼と、将来を見据えた十分な話し合いにかかっています。そして、その複雑性ゆえに、法律、税務、登記、金融といった多岐にわたる専門知識を持つ信頼できる専門家のサポートが不可欠です。実績と専門性を兼ね備え、ご家族の状況に寄り添った提案ができる専門家を選ぶことが、家族信託を円滑に進め、ご自身の思い描く未来を実現するための鍵となります。
家族信託は、ご自身の「安心」とご家族の「確実な未来」を築くための、現代社会に即した有効な選択肢です。この「家族信託大辞典」が、ご自身とご家族にとって最適な未来設計を考える一助となれば幸いです。