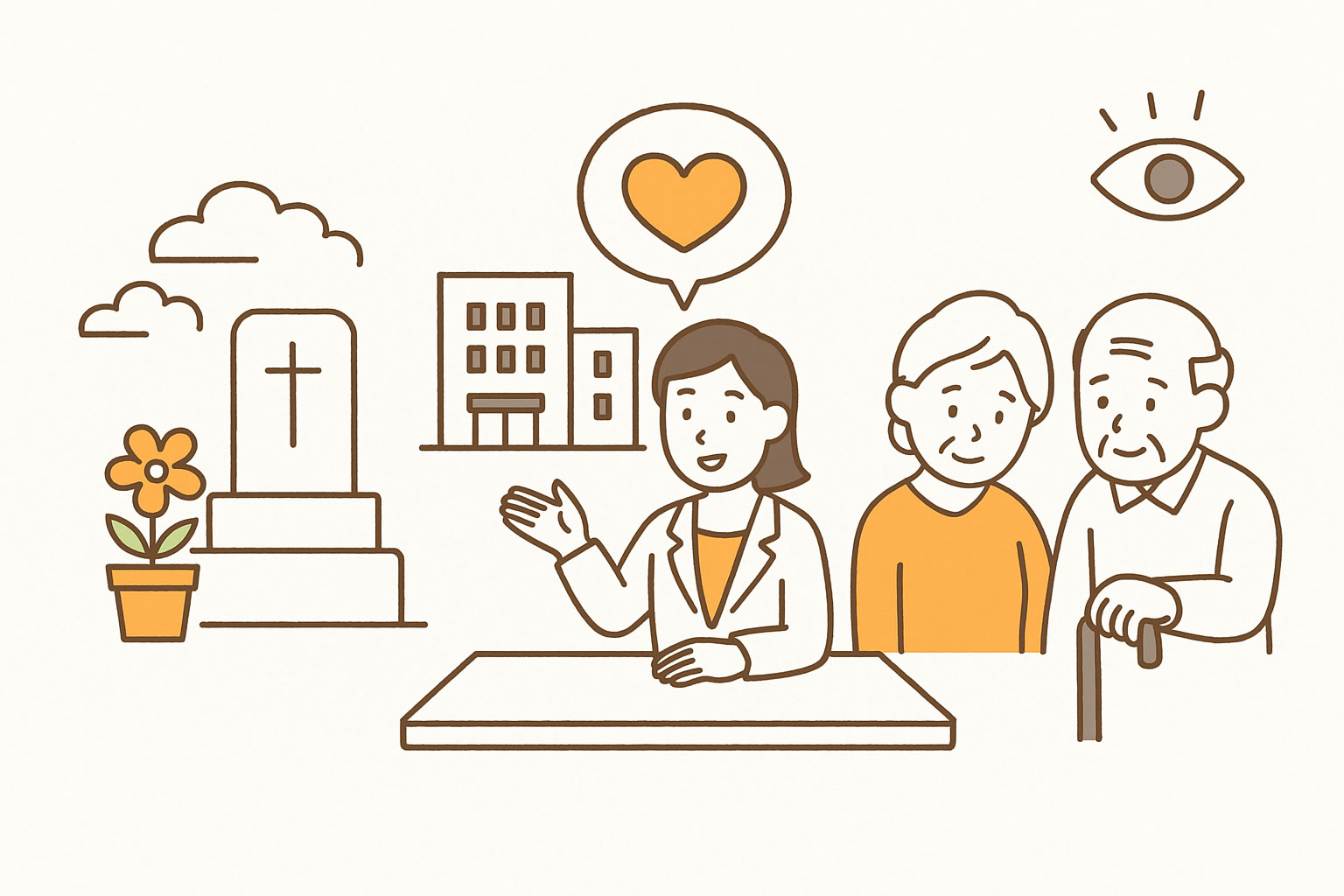はじめに:終活支援の現代的意義
「終活」とは、人生の最終段階をより良く生きるための準備活動全般を指します。これは単に死後の手続きに留まらず、医療や介護に関する準備、財産の整理、遺言書の作成、エンディングノートの活用、さらには周囲の人々への感謝の気持ちを伝えることなど、多岐にわたる活動を含みます。この広範な定義は、終活が単なる「死への準備」ではなく、「人生を最後まで豊かに生きるための準備」であることを示唆しています。
現代の日本社会は、急速な高齢化と少子化、核家族化の進行という構造的変化に直面しています。特に、単身高齢者(いわゆる「おひとりさま」)の数は著しく増加しており、2020年には約670万人であった単身高齢者は、2040年には約900万人に達すると予測されています。さらに、2050年には65歳以上の独居高齢者世帯が5人に1人に上る見通しであり、この人口動態は社会に深刻な影響を及ぼしています。
このような背景のもと、「身寄りがない」ために、自身の死後の手続きや葬送、遺品整理などに不安を抱える人々が増加しています。その結果、引き取り手のない遺骨(無縁遺骨)の増加、遺留金品の処理問題、そして孤独死といった社会問題が顕在化しています。これらの問題は、個人の尊厳が損なわれるだけでなく、自治体にとって大きな行政的・財政的負担となっています。こうした状況から、個人の尊厳を守り、社会的な負担を軽減するために、自治体による終活支援の必要性が喫緊の課題として認識されています。
自治体による終活支援の現状と課題
終活支援の主要な取り組み内容
自治体が提供する終活支援は、その範囲と深度において多様ですが、主に以下の内容が含まれます。
- 身元保証・見守り: 医療機関への入院や介護施設への入所時に必要となる身元保証の支援、日常的な安否確認、そして緊急時の連絡先の受託などが挙げられます。特に、身寄りがない人々にとって、これらの支援は生活の安心を確保する上で不可欠です。
- 死後事務手続き: 葬儀や納骨に関する支援、死亡時の遺体引き取り、故人の住居の原状回復、残存家財や遺品の処分、公共料金や賃貸契約の解約手続きなどが含まれます。これらの手続きは、故人の意思を尊重し、残された社会への影響を最小限に抑える上で重要です。
- 相続・財産管理: 財産の整理、遺言書の作成支援、税金対策、不動産の名義変更や各種手続きの代行など、専門的な知識を要する分野も終活支援の対象となります。自治体は、これらの分野で専門家への橋渡し役を担うことが多いです。
- 医療・介護に関する準備: 介護保険サービスの利用手続き代行、本人の希望に基づく医療に係る意思決定支援(リビングウィルなど)の確認と記録も、終活の重要な要素です。
- 情報登録・相談窓口: 緊急連絡先、持病、葬儀の生前契約、エンディングノートの保管場所など、万一の際に必要な情報をあらかじめ自治体に登録できる制度や、終活全般に関する無料相談窓口の設置が進められています。
無縁仏・孤独死対策の現状
無縁仏の増加は、自治体にとって深刻な問題です。全国の市区町村が保管する引き取り手のない遺骨は、2021年10月時点で約6万柱に上ることが判明しており、その数は増加傾向にあります。これらの遺骨の保管・管理、そして火葬・埋葬にかかる費用は自治体が負担しており、遺留金がある場合はそこから充当されますが、不足分は公費で賄われます。また、死亡人の戸籍調査や親族関係図の作成、遺留金品の現金化といった事務手続きは、多くの場合、他の業務と兼務する少数の職員によって行われており、大きな業務負担となっています。特に、身元が判明しているにもかかわらず、親族が不明、あるいは引き取りを拒否するといった理由で引き取り手のない遺骨が増えている点が、現代の無縁仏問題の大きな特徴です。
孤独死を防ぐための見守り制度も、多くの自治体で実施されています。そのアプローチは多岐にわたります。
- 伝統的見守り: 民生委員や社会福祉協議会(社協)の職員が、一人暮らしの高齢者の自宅を定期的に訪問し、安否確認や対話を通じて孤独感を和らげる活動が行われています。また、電話やはがきによる安否確認も、訪問に抵抗がある高齢者向けに実施されています。
- 地域連携型見守り: 地域コミュニティや多様な民間事業者との連携を強化する動きも活発です。世田谷区では、新聞販売店、ライフライン事業者(電気、ガス、水道)、宅配業者、金融機関、コンビニエンスストア、スーパーマーケットなど、日常生活に関わる広範な事業者と「高齢者見守り協定」を締結しています。これらの事業者は、業務中に高齢者の異変(例えば、異臭、倒れている、連絡が取れない、配達物がたまっている、認知症の疑いなど)に気づいた際に、自治体の地域包括支援センターに通報する仕組みを構築しており、地域全体で高齢者を見守る重層的なネットワークが形成されています。
- デジタル・テクノロジー活用: 近年では、テクノロジーを活用した見守りも導入されています。人感センサー、ベッドに取り付ける圧力センサー、温湿度センサー、窓やドアの開閉センサーなど、プライバシーに配慮しつつ異変を察知するIoT機器が利用されています。例えば、北海道七飯町では「いまイルモ」システムを導入し、高齢者の日常の行動データをモニタリングし、家族や自治体と共有することで健康管理や病気予防にも役立てています。また、センサー付き電球やAI映像解析による転倒事故の早期発見など、より高度な技術も民間企業から提供されています。
しかし、これらの見守り制度にも課題が存在します。多くの見守り制度が65歳以上や70歳以上といった特定の高齢者層に限定されており、65歳未満の独居者の孤独死への対応が難しいという問題が指摘されています。また、特にデジタルツールを用いた見守りにおいては、効果的な安否確認と個人のプライバシー保護とのバランスをどのように取るかが常に問われます。さらに、相談はあっても実際の情報登録に至らないケースが多いことや、紙ベースの登録・更新の煩雑さが、利用促進の障壁となっていることも課題として認識されています。
自治体終活支援の法的位置づけと限界
自治体による終活支援の法的位置づけには、依然として曖昧な部分が存在します。「行旅病人及行旅死亡人取扱法」や「墓地、埋葬等に関する法律」は、身寄りのない死亡人の処理に関する規定を有していますが、現代の「身元が判明しているが引き取り手のない遺骨」や、それに伴う「遺留金品の処理」については、自治体の業務に関する明確な法令上の規定が不足しています。これにより、自治体は法的な根拠が不明確な中で、増加する無縁遺骨や遺留金品の問題に対処せざるを得ない状況にあります。
また、行政手続きの範囲にも限界があります。自治体は、身寄りのない者の死亡時に火葬や埋葬を行うことはできますが、それ以上の広範な死後事務(例えば、遺品整理、賃貸契約の解約、公共料金の精算、デジタル遺品の処理など)は原則として行いません。これらの手続きは、死後事務委任契約などの民間サービスや、個人の生前準備によって補完されるべき領域とされています。
成年後見制度も、判断能力が低下した高齢者の財産管理や生活支援を行う重要な制度ですが、終活の包括的なニーズに応えきれていない側面があります。成年後見制度は、裁判所の監督下にあるため、財産活用における柔軟性に欠け、本人の財産保護が最優先されるため、他の親族のための財産使用や積極的な資産運用はできません。また、弁護士等の専門家が成年後見人となる場合、月額3万円から5万円程度の報酬が発生し、さらに後見監督人が選任されると追加報酬がかかるため、支出が高額になる傾向があります。一度選任されると、特別な理由がない限り本人が死亡するまで解任できないといったデメリットもあり、これらの制約が、終活における個人の多様なニーズへの対応を難しくしています。
全国自治体の取り組み事例と実体
先進的な終活支援モデル
全国の自治体では、高齢化の進展と「おひとりさま」の増加に対応するため、様々な終活支援モデルが展開されています。
- 神奈川県横須賀市:全国に先駆けて終活支援に取り組む先進事例として広く知られています。横須賀市では、引き取り手のない遺骨が過去30年間で5倍に増加したという深刻な状況に直面し、行政の役割を再定義する必要性を強く認識しました。
- エンディングプラン・サポート事業(ES事業):2015年7月に開始されたこの事業は、身寄りのない低所得の単身高齢者を対象としています。利用者は市の協力葬儀社と生前契約を結び、費用を預けることで、亡くなった後に市と協力葬儀社が連携して葬儀や納骨を行います。費用は26万円(生活保護受給者は5万円)に抑えられており、利用者の生前の意向を尊重した葬送が実現されています。この事業は、市が全ての葬儀を請け負うよりも市税の削減(1000万円以上)にも貢献しており、行政が単なる「処理」から「尊厳ある支援」へと役割を転換した象徴的な取り組みとして評価されています。
- 終活情報登録伝達事業:2018年5月からは、緊急連絡先、エンディングノートの保管場所、墓の所在地など計11項目の情報を市に登録できる制度も開始しました。年齢や所得による利用制限はなく、登録者は670人を超えています。万一の際に、警察や医療機関などからの照会に対し、市が登録情報を伝えることで、本人の意思を尊重した対応を可能にしています。この事業は、引き取り手のない遺骨の問題が、生前の「身寄りなし」問題や死後の遺留金品、空き家問題と根本的に同じであるという認識に基づいています。
- 東京都豊島区:都内23区で初めてとなる終活に関する専用窓口を設置しました。
- 終活あんしんセンター:2021年2月に開設され、区から委託を受けた区民社会福祉協議会(社協)が運営しています。相続、遺言、葬儀など終活全般について相談を受け付けており、これまでの累計相談件数は約2000件に上ります。センターが社協内に設置されているため、見守り訪問や成年後見制度の利用支援など、社協の既存サービスに円滑につながるケースが多い点が特徴です。社協はさらに、2024年度から日常の見守り、入退院支援、葬儀、家財処分などをパッケージ化した新規事業も計画しており、終活支援の範囲を広げています。
- 終活情報登録事業:2022年4月からは終活情報登録事業も開始しています。
- 愛媛県今治市:2025年1月に、愛媛県内で初めて自治体主導による「終活サポート事業」を開始しました。人口減少と2023年には35.8%に達した高齢化率という課題に対し、「住み続けたい田舎」を実現するための一環として位置づけられています。
- 終活サポートセンターの開設、終活情報登録事業の実施、そして出張講座の開催を通じて、市民が家庭内で終活について話し合うきっかけ作りを促進しています。この取り組みは、高齢化が進む地方自治体のモデルケースとしても注目されています。
- 神奈川県大和市:2021年7月1日に「大和市終活支援条例」を施行し、終活における市の責務や市民、事業者の役割を明確化しました。また、「わたしの終活コンシェルジュ」を設置し、一人暮らしの高齢者などを対象に、終活に関する相談に応じています。協力葬祭事業者の紹介、遺品整理の専門家手配、エンディングノートの配布と市による保管サービスなど、多角的なサポートを行っています。
- 香川県坂出市:高齢者を対象に「終活サポート窓口」を開設し、終活にかかわる事業を行う専門職や民間事業者を紹介する形での支援を行っています。市は契約への立ち会いや補助金の支給は行わない、紹介に特化したモデルであり、比較的少ないリソースで終活相談のニーズに応えるアプローチと言えます。
独居老人へのケアサービスと見守りの実態
自治体は、独居高齢者の孤立死防止と生活の質の維持のため、多岐にわたるケアサービスと見守り活動を展開しています。
- 多様な見守りアプローチ:
- 訪問による見守り: 最も直接的な方法として、民生委員や社会福祉協議会職員が定期的に高齢者の自宅を訪問し、安否確認を行うとともに、対話を通じて孤独感を和らげる役割を担っています。春日井市では、75歳以上の高齢者が民生委員による「地域の実情把握調査」に協力することで、自動的に「ひとり暮らし高齢者登録制度」に登録されるという、既存の地域ネットワークを最大限に活用した先進的な取り組みが行われています。
- デジタルツールによる見守り: テクノロジーの進化に伴い、センサー付き電球、人感センサー、エアコンの「ひと検知」機能、AI映像解析など、高齢者のプライバシーに配慮しつつ異変を察知するデジタルツールの導入が進んでいます。例えば、北海道七飯町の「いまイルモ」システムは、高齢者の日常の行動データをモニタリングし、そのデータを家族や自治体の職員と共有することで、生活習慣の見直しや病気予防にも役立てるという、予防的なケアの側面も持ち合わせています。
- 地域コミュニティ・民間事業者との連携: 自治体は、地域包括支援センターを中心に、地域の住民、ボランティア、そして多様な民間事業者との連携を強化しています。世田谷区の「高齢者見守り協定」は、この連携モデルの先進事例であり、新聞販売店、ライフライン事業者、宅配業者、金融機関、コンビニエンスストアなど、高齢者の日常生活に深く関わる広範な事業者と協定を締結しています。これらの事業者は、業務中に高齢者の「気になる状況」(例えば、異臭、家の中で倒れている、連絡が取れない、配達物がたまっている、認知症の疑いなど)に気づいた際に、自治体のあんしんすこやかセンターに通報する仕組みを構築しており、地域全体で高齢者を見守る重層的で漏れのないネットワークを形成しています。
- 電話・はがきによる見守り: 訪問が難しい場合や、見守られることに抵抗がある高齢者向けに、電話やはがきで定期的に安否や健康状態を確認するサービスも提供されています。
- 支援金等による見守り: 自治体が民間事業者の見守り活動や、民生委員の訪問活動を補完する新たな取り組みに対して補助金を交付し、サービス拡充を支援するケースも存在します。
- 「地域包括支援センター」の役割: 地域包括支援センターは、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を継続できるよう、医療と介護の橋渡し役を担う中核的な拠点として位置づけられています。多くの自治体で終活相談窓口がこれらのセンター内に設置され、相続税などの専門的な相談にも対応できる体制が強化されており、終活支援においても中心的な役割を果たすことが期待されています。
今後期待される終活支援制度の中身
包括的・統合的な支援体制の構築
超高齢社会の進展に伴い、終活支援はより包括的かつ統合的なアプローチが求められています。
- ワンストップ窓口の強化: 死亡に伴う行政手続きは多岐にわたり、遺族が複数の窓口を回る負担は非常に大きいものです。この負担を軽減するため、ワンストップで相談から手続きまでが完結する窓口の設置が喫緊の課題です。福山市や千葉市では、死亡届出後の手続きをまとめて受け付け、申請書の記入省略や予約制による待ち時間短縮を図る「おくやみワンストップ窓口」を導入し、遺族の負担軽減に貢献しています。将来的には、市役所以外の機関(例えば、金融機関や年金事務所など)への手続き案内も含む、より包括的なワンストップサービスが求められます。
- 公私連携の深化: 自治体だけでは終活に関する全てのニーズに対応することは困難です。そのため、民間事業者(葬儀社、遺品整理業者、弁護士、司法書士、行政書士など)や社会福祉協議会との連携を一層強化し、行政が直接提供できない専門的なサービスへのアクセスを確保することが不可欠です。特に、身寄りがない高齢者に対する身元保証や死後事務の提供においては、公的な支援と民間サービスの連携がより重要となります。民間サービスは費用がかかるという課題があるため、公的機関が連携を強化することで、サービスの選択肢を広げ、質の向上を図りつつ、適切な情報提供を行う必要があります。
- 「身寄りなし」問題への対応強化: 「身寄りなし」の状況は、無縁遺骨や遺留金品の問題、空き家の問題、医療・介護施設への入所問題など、多岐にわたる課題の根源です。自治体は、こうした複合的な課題に対し、包括的な情報登録制度や、民間サービスでは対応が難しい低所得者層向けの身元保証・死後事務支援を拡充する必要があります。厚生労働省のモデル事業のように、十分な資力がない人々が支援の狭間に落ちないよう、公的支援の枠組みを広げることが期待されます。
デジタル化とテクノロジーの活用
終活支援の効率化と質の向上には、デジタル化とテクノロジーの活用が不可欠です。
- 情報登録・管理のデジタル化: 現在、紙ベースで煩雑な終活情報の登録・更新プロセスは、利用者の負担を大きくしています。これをデジタル化することで、利用者の負担を軽減し、情報の正確性と活用度を高めることができます。これにより、緊急時や死亡時に必要な情報が迅速かつ正確に関係機関に伝達される「プッシュ型」の通知システムの構築が可能となり、情報の活用不足という課題を解消できます。
- 見守りサービスの高度化: IoTセンサーやAIを活用した見守りシステムは、高齢者のプライバシーに配慮しつつ、より効率的かつ継続的な安否確認を可能にします。自治体は、これらの先進技術の導入を推進するとともに、導入費用への助成や、地域の実情に応じた技術選定・導入支援を行うべきです。ただし、テクノロジー導入においては、誤作動の不安や利用者の抵抗感を払拭するための丁寧な説明と信頼関係の構築が不可欠であり、技術的な側面だけでなく、利用者の心理的な側面への配慮が求められます。
制度設計と人材育成
終活支援を実効性のあるものにするためには、制度設計の改善と専門人材の育成が不可欠です。
- 終活支援の専門人材育成: 終活に関する相談は、法律、税務、医療、介護、心理など多岐にわたる専門知識を要します。現在の相談対応者の要件が「特になし」という現状は、サービスの質を担保する上で課題であり、専門的な知識を持つ相談員の育成・配置、あるいは外部の専門家との連携体制の強化が不可欠です。終活アドバイザーのような民間資格者を行政の「橋渡し役」として活用しつつ、その質の担保と継続的な研修が求められます。
- 柔軟な費用負担モデルの検討: 民間サービスの費用が高額である点は、低所得者層にとって大きな障壁となります。公的支援においては、一括預託金が困難な低所得者向けに月額払いなど、より柔軟な費用負担モデルを導入することが望ましいです。これは、経済的な理由で終活支援から取り残される人々をなくすために重要です。
- 法整備の推進: 無縁遺骨や遺留金品の処理に関する自治体の業務について、明確な法的規定が不足している現状を解消するため、国レベルでの法整備やガイドラインの策定が急務です。内閣府が策定した「高齢者向け終身サポート事業者ガイドライン」は民間事業者を対象としていますが、その原則は自治体の終活支援にも応用可能であり、消費者保護の観点から参照されるべきです。これにより、自治体の法的・行政的負担を軽減し、より安定したサービス提供が可能となります。
結論と提言
終活支援は、単に個人の死後準備に留まらず、超高齢社会における個人の尊厳保持、家族機能の補完、そして自治体の行政負担軽減という多角的な課題解決に資する重要な取り組みです。現在の自治体の取り組みは、相談窓口の設置や情報登録事業、見守り活動など多岐にわたりますが、その多くはまだ限定的であり、特に「身寄りなし」の高齢者に対する包括的な支援や、デジタル技術の活用、専門人材の確保には課題が残されています。
今後、自治体は以下の点に注力し、より実効性の高い終活支援体制を構築することが強く提言されます。
- 包括的ワンストップ支援の実現: 複雑な終活・死後手続きを統合し、相談から実行までを一貫してサポートするワンストップ窓口の整備を加速させるべきです。これは、遺族や本人の負担を大幅に軽減し、行政手続きの円滑化に繋がるものです。
- 公私連携の戦略的強化: 民間事業者や社会福祉協議会、地域コミュニティとの連携を一層深化させ、それぞれの強みを活かした多層的な支援ネットワークを構築すること。特に、費用面で民間サービスを利用しにくい層への公的支援の拡充が不可欠です。
- テクノロジーの積極的導入と活用: IoTを活用した見守りシステムの導入や、終活情報登録のデジタル化を推進し、効率的かつ質の高いサービス提供を目指すこと。その際、プライバシー保護と利用者への丁寧な説明を徹底し、技術への抵抗感を払拭する努力が求められます。
- 専門人材の育成と法整備の推進: 終活支援に関わる職員の専門性向上に向けた研修体制を確立し、必要に応じて外部専門家との連携を強化すること。また、無縁遺骨や遺留金品処理に関する自治体の業務を明確化する法整備を国に働きかけ、自治体の法的・行政的負担を軽減する必要があるでしょう。
- 「終活」のポジティブな啓発: 「終活」が人生の終末を前向きに捉え、安心して生きるための準備であることを広く啓発し、市民が主体的に終活に取り組むきっかけを提供すること。家族間での話し合いを促すような出張講座やイベントの継続的な開催も有効です。
これらの取り組みを通じて、自治体は「多死社会」における新たな社会インフラとして、市民が安心して人生の最終章を迎えられるよう、その役割を一層強化していくことが期待されます。