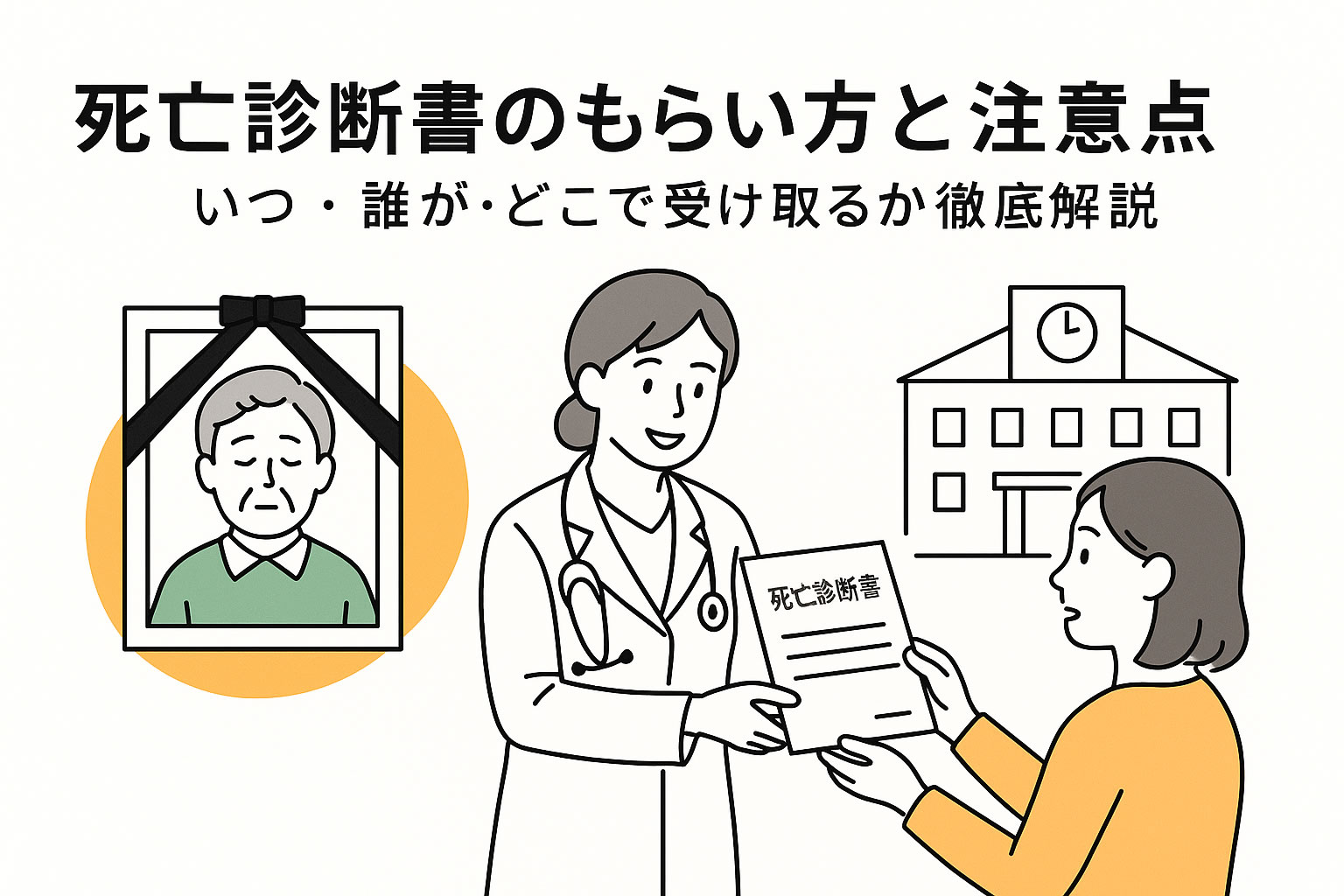✅ 死亡診断書とは何か?
死亡診断書(しぼうしんだんしょ)とは、医師が人の死亡を確認したときに発行する公式な証明書です。この診断書は、役所へ提出する「死亡届」と一体型になっており、故人の死亡を公的に証明し、その後のすべての公的手続き(葬儀、火葬、保険金請求、年金手続き、遺産相続など)の出発点となります。
✅ どこでもらえる?誰が発行する?
死亡診断書は、故人が亡くなった状況によって発行者や受け取り場所が異なります。
| 状況 | 発行者・受け取り場所 | 補足 |
|---|---|---|
| 病院で亡くなった場合 | 担当医師が作成し、病院の窓口または病棟で受け取る | 主治医または担当医が発行します。 |
| 自宅で亡くなった場合 | 訪問医または搬送先の病院の医師が発行 | かかりつけ医がいる場合は訪問医に連絡。いない場合は救急搬送された病院の医師が発行します。 |
| 急死・事故死など | 警察の検視後、監察医または警察指定の医師が作成し、死体検案書として発行 | 事件性や不審な点がある場合、警察による検視・検案が行われます。 |
✅ 死亡診断書の記載内容(主な項目)
死亡診断書には、法的に定められた重要な情報が記載されます。
- 故人の情報: 氏名、生年月日、性別、本籍、住所など
- 死亡日時・場所: 死亡した正確な日時(西暦、元号)、死亡した場所の名称(病院名、住所など)
- 死因:
- 直接死因: 最終的に命を奪った病気や外因(例:肺炎、脳出血、交通事故による外傷)
- 基礎疾患: 直接死因に至った原因となった病気や既往歴(例:心不全、糖尿病、がん)
- その他特記事項: 死亡に至るまでの経緯や、死因の特定に影響する情報
- 死亡の種類: 病死、外因死(事故、自殺など)、不詳の死など
- 診断を行った医師の署名・捺印: 診断した医師の氏名、医療機関名、所在地、医師免許番号、診断年月日などが記載されます。
- 死亡届(裏面): 死亡診断書と一体になっている裏面には、届出人の情報(氏名、住所、故人との続柄など)、世帯主の情報、葬儀を行う場所などの項目があり、届出人が記入します。
⚠️ 死亡届と一体型のため、折り曲げたり汚したりしないよう注意が必要です。ホチキス止めされている場合は、そのまま使用しましょう。
✅ 診断書が発行されるまでの流れ
死亡診断書が発行されてから、死亡届の提出に至るまでの一般的な流れは以下の通りです。
- 医師が死亡を確認: 医師が臨終に立ち会い、心肺停止や瞳孔散大などの身体的所見を確認し、死亡を判断します。
- 死因等を診断・記載: 医師が故人の病状や経過に基づき、死亡診断書に死因や死亡日時などの必要事項を記載します。
- 遺族へ死亡診断書を交付(通常1通): 病院のスタッフや医師から、遺族(通常は配偶者や子など)に死亡診断書が手渡されます。この際、今後の手続きに関する説明を受けることもあります。
- 葬儀社が火葬手配に使用/遺族が死亡届として役所に提出: 交付された死亡診断書は、多くの場合、葬儀社に渡され、葬儀社が死亡届の提出や火葬許可証の申請を代行します。遺族自身が役所に提出することも可能です。
※追加で必要な場合、有料でコピーや再発行ができることもあります。しかし、原本は1通のみであるため、必要な枚数を事前に確認し、慎重に取り扱いましょう。
✅ 診断書が発行されるまでの流れ
- 医師が死亡を確認
- 死因等を診断・記載
- 遺族へ死亡診断書を交付(通常1通)
- 葬儀社が火葬手配に使用/遺族が死亡届として役所に提出
※追加で必要な場合、有料でコピーや再発行できることもあります。
✅ 死亡診断書の複数枚発行について
死亡診断書の原本は通常1通のみ発行されますが、様々な手続きで提出を求められる場合があります。事前に必要枚数を把握し、備えておくことが重要です。
- 提出先ごとの必要枚数: 役所(死亡届)、火葬場、生命保険会社、銀行(故人の口座解約・名義変更)、証券会社、法務局(相続登記)、税務署(相続税申告)など、多くの手続きで原本または写しの提出が求められることがあります。
- 「死亡診断書の写し」と「死亡証明書」:
- \*\*写し\*\*: 死亡診断書をコピーしたものです。公的な手続きでは原本を求められることが多いですが、写しで対応できる場合もあります。
- \*\*死亡証明書\*\*: 病院が死亡の事実を独自に証明する書類です。金融機関などで、死亡診断書の代わりとして利用できるケースがあります。
- 再発行について: 紛失したり、追加で必要になったりした場合、発行元の病院に依頼すれば再発行が可能です。ただし、有料であり、発行には数日〜数週間かかる場合があるため、余裕を持って申請しましょう。
✅ 死亡診断書と検案書の違い
| 書類名 | 発行者 | 主なケース | 補足 |
|---|---|---|---|
| 死亡診断書 | 医師 | 病気や老衰による自然死、かかりつけ医による看取り | 生前の治療や経過が明らかで、死因に不審な点がない場合。 |
| 死体検案書 | 警察経由+医師(監察医など) | 急死・事故死・不審死など | 死亡に事件性や事故の可能性、死因不明などの疑いがある場合。 |
「検案書」になる場合は、死因調査に時間がかかるため、その後の火葬や手続きも遅れることがあります。この場合、警察による事情聴取などが行われることもあります。
✅ 注意点・よくある疑問
火葬や埋葬許可の申請にはこの書類が必須: 死亡診断書(または死体検案書)がないと、火葬や埋葬の許可が下りません。
受け取る際の確認事項
- 記載内容の誤りがないか: 故人の氏名、生年月日、死亡日時、死因などに誤りがないか、その場で必ず確認しましょう。特に\*\*戸籍上の氏名と死亡診断書上の氏名が一致しているか\*\*は重要です。
- 訂正方法: 万が一、記載内容に誤りがあった場合の訂正方法(医師に訂正印を押してもらう、再発行など)を確認しておくと安心です。
- 発行手数料: 死亡診断書の発行には費用がかかります。通常、数千円から1万円程度が目安ですが、病院によって異なるため、事前に確認し、準備しておくとスムーズです。
- 火葬や埋葬許可の申請にはこの書類が必須: 死亡診断書(または死体検案書)がないと、火葬や埋葬の許可が下りません。
- 紛失しないよう、受け取ったらすぐコピーを取り保管: 原本は死亡届として役所に提出するため、手元に残りません。今後の手続きで必要になる場合があるので、必ず複数枚コピーを取っておきましょう。
- コピー提出では認められない場合がある(役所・保険会社など): 公的な手続き(年金、保険金請求など)では、死亡診断書の「写し」や「死亡証明書」といった原本の代わりになる書類の提出を求められることがあります。事前に各機関に確認しましょう。
- 死亡診断書の費用: 病院や状況によって異なりますが、一般的に数千円から1万円程度かかることが多いです。急な出費となるため、事前に確認しておくと良いでしょう。
🧾 死亡診断書を受け取ったら、次にすべきこと
死亡診断書を受け取った後の、主な手続きの流れは以下の通りです。時間制限のある手続きも多いため、速やかに対応しましょう。
- 死亡届を作成して役所に提出(7日以内): 死亡診断書の裏面にある死亡届に必要事項を記入し、故人の本籍地、死亡地、または届出人の住所地の市区町村役場に提出します。原則として死亡を知った日から7日以内(国外で死亡した場合は3ヶ月以内)に提出する必要があります。
- 火葬許可証の発行手続き: 死亡届を提出する際に、同時に火葬許可申請書を提出し、火葬許可証を発行してもらいます。この許可証がないと火葬を行うことができません。
- 葬儀社との打ち合わせ・段取りの確定: 葬儀の日程、場所、形式などを葬儀社と具体的に決定します。葬儀社が死亡届の提出などを代行してくれる場合が多いです。
- 年金や保険の申請準備へ進む: 死亡届の提出が完了したら、故人が加入していた年金や健康保険の資格喪失手続き、生命保険や医療保険の保険金請求手続きなど、必要な書類の準備を始めます。
📥 手続きの流れを見える化したチェックリストも配布中!
チェックリストを今すぐダウンロードする(PDF)🔚 まとめ:死亡診断書はすべての手続きの起点
死亡診断書は、法的に「亡くなったことを証明する唯一の書類」です。医師による正式な書類なので、確実に受け取り・紛失しない管理が非常に重要です。
この書類がなければ、その後の葬儀、火葬、各種公的な手続き(年金、健康保険、生命保険、相続など)を一切進めることができません。スムーズに次の「死亡届」や「火葬手続き」に移行できるよう、内容をよく確認し、大切に保管しましょう。
ご不明な点があれば、病院の相談窓口や葬儀社に相談することをおすすめします。
死亡診断書の全てがわかる:死亡診断書大辞典